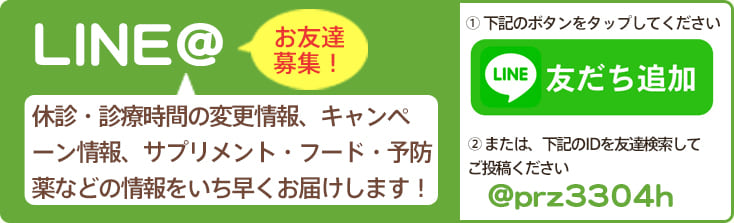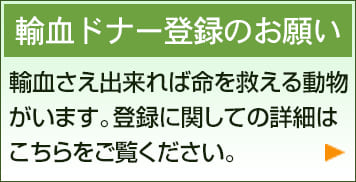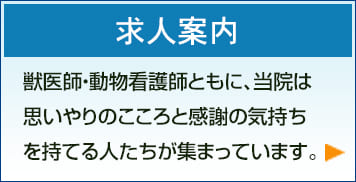ネコちゃんとの暮らしで気を付けていただきたい予防や病気についてなど、ネコちゃんとの楽しい暮らしが続くために必要なことをお伝えしています。
年齢ごとに気をつけたい暮らしの情報については
「10歳までのネコちゃん」、「11歳以上のネコちゃん」、の各ページをご覧ください。
子猫をお家に迎えたら
子猫の時期は、最も手のかかる時期であり、一番大切な時期でもあります。猫の性格、体質、好みなどはほとんど子猫の時期に決まってしまうため、様々な経験をさせて適応能力をつけることが、家族として、また社会の一員として幸せに暮らすために必要です。
| 時期 | 実施していただきたいこと |
|---|---|
| 2か月前後 |
|
| 3~4ヶ月 |
|
| 4~5ヶ月 |
|
| 6カ月~ |
|
| ~12か月 |
|
| 1歳~ |
|
 ネコちゃんの社会化期について
ネコちゃんの社会化期について
ネコちゃんの社会化期(モノや人になれやすい時期)は約3~7週齢とワンちゃんより短い傾向にあります。 この時期に新しい環境や病院、他のペットや来客に慣らすことで、スムーズに人間社会に溶け込めます。
お手入れ習慣を身につけましょう
ネコちゃんの場合、トイレのしつけ以外は難しいこともあり、一般的ではありません。しかし、今後の定期的な健康管理の為にも、全身を触れれる事・口腔内を触られることには慣れさせていきましょう。
1.全身に異常がないかチェック
 スキンシップを兼ねて全身を触って細かくチェックしたり、普段の行動を観察して異常がないか確認をしましょう。
スキンシップを兼ねて全身を触って細かくチェックしたり、普段の行動を観察して異常がないか確認をしましょう。
- ・元気(動き、歩き方、鳴き方など)
- ・排尿(回数、色、ニオイ)
- ・食欲(食べる量)
- ・被毛や皮膚の異常(傷、痛み、しこり)
- ・飲水(水を飲む量)
- ・耳、目、鼻の状態の観察
- ・排便(回数・状態)
- ・口の中のにおい(嫌な臭いは異常のサイン)
2.毎日の歯磨きを
 ネコちゃんの口の中は酸性の為、虫歯にはなりませんが、歯周病にはなりやすい特徴があります。
ネコちゃんの口の中は酸性の為、虫歯にはなりませんが、歯周病にはなりやすい特徴があります。
歯周病は口腔内だけでなく心疾患など全身の健康問題につながります。
歯ブラシを嫌がる場合は歯磨きジェルをつけたガーゼ等でふくことも効果があります。
3.耳掃除は控えめに
 ご家庭での耳掃除はコットンを使って表面を優しくふく程度にしてあげてください。綿棒を使用すると傷がついてしまったり、痛がって嫌がるようになります。
ご家庭での耳掃除はコットンを使って表面を優しくふく程度にしてあげてください。綿棒を使用すると傷がついてしまったり、痛がって嫌がるようになります。
4.痛みのサインについて
 ネコちゃんは症状を隠そうとしがちです。また、痛みを行動で訴えることがあります。性格により異なりますが、『いつもと違う』と感じたら、その他の症状や原因となるものがないかよく観察し、ご相談ください。
ネコちゃんは症状を隠そうとしがちです。また、痛みを行動で訴えることがあります。性格により異なりますが、『いつもと違う』と感じたら、その他の症状や原因となるものがないかよく観察し、ご相談ください。
- ・落ち着かない
- ・呼吸が早い
- ・攻撃的になる
- ・隠れる
- ・うずくまる
- ・食欲がなくなる
- ・特定の部位をしきりに舐める
基本となる予防を継続的に行いましょう
1.ワクチン接種
 当院では3種及び5種類の病気を予防できるワクチンをお勧めしています。特にお外に出てしまうネコちゃんは感染する病気の数も多くなります。しっかりと予防してあげてください。毎年1回の接種が必要です。
当院では3種及び5種類の病気を予防できるワクチンをお勧めしています。特にお外に出てしまうネコちゃんは感染する病気の数も多くなります。しっかりと予防してあげてください。毎年1回の接種が必要です。
2.ノミ・ダニ予防
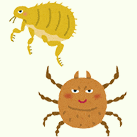 ネコちゃんにノミ・ダニが寄生すると皮膚炎や病気を引き起こします。 また、ネコちゃんに付いたノミやダニは飼主様を刺すこともあり、人にも感染する、人と動物の共通感染症を引き起こします。ここ数年で感染が確認されており人の死亡例もあるSFTSなどもその1つです。
ネコちゃんにノミ・ダニが寄生すると皮膚炎や病気を引き起こします。 また、ネコちゃんに付いたノミやダニは飼主様を刺すこともあり、人にも感染する、人と動物の共通感染症を引き起こします。ここ数年で感染が確認されており人の死亡例もあるSFTSなどもその1つです。
またノミが媒介するお腹に寄生する瓜実条虫やダニが媒介するリケッチアウイルスなどがあります。
3.フィラリア予防
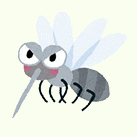 フィラリア症はワンちゃんだけの病気と思われがちですが、ネコちゃんにも感染する病気です。 ネコちゃんが感染するとワンちゃんに比べ死亡するリスクが高くなってしまいます。フィラリア症は蚊が媒介して起こる病気ですが100%予防できる病気でもあります。
フィラリア症はワンちゃんだけの病気と思われがちですが、ネコちゃんにも感染する病気です。 ネコちゃんが感染するとワンちゃんに比べ死亡するリスクが高くなってしまいます。フィラリア症は蚊が媒介して起こる病気ですが100%予防できる病気でもあります。
この地域では4月末から12月の9回の予防が必要です。
ネコちゃんにお勧めしている検査
1.ウイルス検査
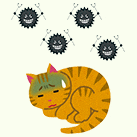 院内のウイルス検査では、① 猫免疫不全ウイルス(FIV) ② 猫白血病ウイルス(FeLV)という2つの感染症を調べることができます。感染の有無を定期的に調べておくことをお勧めしています。少量の採血をするだけで検査が可能ですので、小さな子猫でも安心して検査を受けていただけます。
院内のウイルス検査では、① 猫免疫不全ウイルス(FIV) ② 猫白血病ウイルス(FeLV)という2つの感染症を調べることができます。感染の有無を定期的に調べておくことをお勧めしています。少量の採血をするだけで検査が可能ですので、小さな子猫でも安心して検査を受けていただけます。
- □ 外に遊びに行く子(少しでも)
- □ 過去の飼育環境がわからない子
- □ 昔、ノラ猫だった子
- □ お母さん猫がノラ猫の子
- □ 多頭飼いのネコちゃん達の中に1頭でもこれらに当てはまる子がいる場合
2.尿検査
 特にネコちゃんは泌尿器系の病気にかかりやすい動物です。そのため最低年に1回は検査を行っていただきたいと考えています。尿検査では、腎臓などの内臓機能、糖尿病の状態、結晶の有無についても調べることができます。ネコちゃんの健康状態を知る、最も簡単な方法ともいえます。
特にネコちゃんは泌尿器系の病気にかかりやすい動物です。そのため最低年に1回は検査を行っていただきたいと考えています。尿検査では、腎臓などの内臓機能、糖尿病の状態、結晶の有無についても調べることができます。ネコちゃんの健康状態を知る、最も簡単な方法ともいえます。
尿検査を行う際はできる限り新鮮な尿が必要です。病院へお持ちいただく際は直前に採れた尿をご持参ください。
年1回以上の健康診断を行いましょう
1.血液検査
 健康診断の基本となる検査です。肝臓・腎臓などの内臓機能の状態や、コレステロール値、糖尿病の状態など様々な健康状態を調べることができます。
健康診断の基本となる検査です。肝臓・腎臓などの内臓機能の状態や、コレステロール値、糖尿病の状態など様々な健康状態を調べることができます。
10歳程度までは年1回、11歳を超えてくると年2回以上の検査をお勧めしています。
2.画像診断(レントゲン検査・エコー検査など)
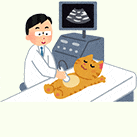 血液検査だけでは分からない身体の状態を詳しく調べることができます。
血液検査だけでは分からない身体の状態を詳しく調べることができます。
特に当院で専門的に行っている循環器の診療ではエコー検査などを用いて、心臓などの循環器の病気の早期発見などにも取組んでいます。
3.便検査
 尿検査では、腎臓機能、糖尿病の状態、結晶の有無についても調べることができます。ワンちゃんの健康状態を知る、最も簡単な方法ともいえます。
尿検査では、腎臓機能、糖尿病の状態、結晶の有無についても調べることができます。ワンちゃんの健康状態を知る、最も簡単な方法ともいえます。
尿検査を行う際はできる限り新鮮な尿が必要です。病院へお持ちいただく際は直前に採れた尿をご持参ください。
4.その他の検査
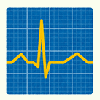 その他にも、心電図検査、内視鏡検査、歯科の検診、眼科の検診、皮膚の健診など、目的に応じた様々な健診を行っております。当院には循環器、腫瘍、整形外科など専門的な知識を有する獣医師も在籍していますので、ネコちゃんの症状などによって最適な検査もご提案させていただきます。
その他にも、心電図検査、内視鏡検査、歯科の検診、眼科の検診、皮膚の健診など、目的に応じた様々な健診を行っております。当院には循環器、腫瘍、整形外科など専門的な知識を有する獣医師も在籍していますので、ネコちゃんの症状などによって最適な検査もご提案させていただきます。
不妊手術について
将来的に子供を作る予定が無い場合には、将来発生する病気のリスクを軽減することを目的として、早い時期の不妊手術をお勧めしています。
メリット
| 避妊手術 (女の子) |
① 特有の行動の減少 発情時特有の神経質な状態や鳴き声の減少、出血がなくなります。 ② 病気の予防(乳腺腫瘍・子宮蓄膿症) 早期に不妊手術を行うと、乳腺腫瘍や子宮蓄膿症などの病気を高い確率で防ぐことが可能です。 |
|---|---|
| 去勢手術 (男の子) |
① 縄張り意識の減少 マーキングやマウンティング、攻撃性の減少が期待できます。 ② 病気の予防(精巣腫瘍・前立腺肥大) 特に前立腺肥大症は、去勢していないワンちゃんが7歳以降に多い病気です。 |
デメリット
| 共通 | エネルギー代謝が落ち太り易くなります。 ・手術前に比べ、20~30%もエネルギー代謝が落ちるといわれています。 ・食事や運動といった管理で体重を維持することが必要になります。 |
|---|
手術のタイミングについて
| 避妊手術 (女の子) |
生後6ヶ月程度で手術を行います。 |
|---|---|
| 去勢手術 (男の子) |
生後6ヶ月程度で手術を行います。 |
食事の管理
ネコちゃんにとって喜びの一つが食事の時間です。とはいえ、飼い主様が食べさせたいものを与えるのではなく、ネコにとって最適な食事を与えられるようにしていきましょう。
1.ペットフードの選び方

- ・良質の原料から作られている
- ・必要な栄養素が適正に含まれている
- ・成長期、成ネコ期、高齢期それぞれライフステージに合わせた選択
2.購入と保存

- ・製造年月日が新しく、開封後2週間で使い切れる量を購入
- ※キャットフード内に含まれている油脂は空気に触れることで変質します。変質した油脂を含む食事を与えると、体調不良等の原因となります。その為、できるだけ2週間以内に使い切れる量をその都度購入するようにしてください。
- ・2週間以上保存する場合は1~2日分ごとに小分けにして冷凍保存または冷蔵
- ※冷蔵庫からの出し入れが多いと、袋の中が結露し、それによってカビが発生する原因となります。難しい場合には、冷暗所で保存することで、品質の低下を抑えることができます。
- ・缶フードは開封後3日以内に使い切る(小分けにして冷凍保存で2週間保存可)
3.与え方の基本

- ・ベストな体重を維持できる適正な量を知る(フードの袋に書いてある場合もあります)
- ・一日の適正量を数回に分けて与える。
- ・新しい食事に切り替える場合は、1週間を目安にこれまでのフードに少量ずつ、日を追うごとに量を増やして切り替えをしていく。
- ・新鮮な水を用意しておく。
- ・間食はさせない(結果的に食べる量が増えてしま、肥満の原因になる)。
4.猫はグルメ

- ・ネコちゃんはグルメなため、一度おいしいものを食べるとそれよりおいしくないものは食べなくなります。
- ・偏食傾向があるため、ドライフードに少量の缶詰を混ぜるなどの変化をつけましょう。
- ・グルーミングの時に胃にたまった毛玉を吐くことがあるため、毛玉の排出にも考慮してあげる。 (猫草や毛玉を考慮したフードを与えるなど)
ネコちゃんが食べてはいけないもの
| 中毒を起こすもの | ・ネギ類 ・カカオ配合物 ・イカ ・カフェイン配合物 ・アワビやサザエなど藻類を食べて育つ貝類 |
|---|---|
| 尿路結石の原因になりやすい | ・鰹節 ・カニカマ ・魚の干物 ・地下水やミネラルウォーター ・煮干し |
| 消化器疾患やショック症状 | ・スズラン ・アジサイ ・ユリ ・スイセン ・ヒヤシンス などの植物 |
| 軟便・下痢 | ・牛乳 |
| 少量でも危険 | ・人の薬 |
| 糖尿病 | ・お菓子などの甘いもの |
お薬の飲ませ方
ネコちゃんにお薬を飲ませる。そのような状況はないのが一番なのですが、もしそのような場合に上手にお薬を飲ませてあげられる方法をお伝えします。
錠剤、カプセルの飲ませ方
- ① 利き手の反対でネコちゃんの頭を持ち上に向ける
- このときの頬骨を持つとやり易いです。鼻が75度ぐらいの角度で持って下さい。45度ぐらいだと投薬はまず失敗します。ネコちゃんの首は人間の腕ぐらいあるので、結構力強いです。 頬骨の位置は目の真横です。よくあるミスとしては顎を持ってしまい、ネコちゃんに嫌がられます。
- ② 利き手で薬を持つ
- 親指と人差し指で薬を持つのがお勧めです。中指は口をあけるためにとっておきましょう。
- ③ 薬を持ったまま口を開ける
- フリーな中指を使って、ネコちゃんの切歯(前歯)に指をかけて口を開けます。ネコちゃんの切歯は非常に小さいです。切歯なら咬まれてもそんなに痛くはありません。
- ④ 薬を落とす
- 舌の付け根を狙って薬を落として下さい。投げ込んではいけません。垂直に顔をあげてればコイン落としのようなイメージで落下させることができます。
- ⑤ フォロー
- しばらく飲み込むまでは利き手の反対を離さず上に向かせ続けて下さい。薬とカプセルは口の中や食道に張り付き易いので注射器などで少量の水を飲ませて下さい。