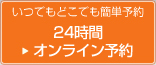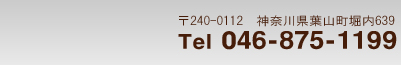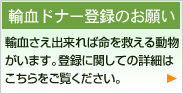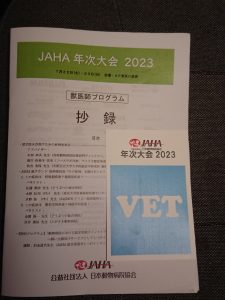中年の雑種犬が他院にて自己免疫性溶血性貧血の診断でステロイドにて治療していたが、脾腫が重度だったため、すぐに脾摘をすすめられた。しかし先行きが不安になったため、ある方と相談したら、当院をご紹介いただき、診察することになった。他院ではヘマトクリットが60%あったものが、数日で37%まで減少し、血色素尿が出ていたので、自己免疫性溶血性貧血と診断して、ステロイドで治療していたが、かなりのスピードで貧血が進行して来たため、セルセプトやその後ガンマーガードまで使ってみたが、数日後にはヘマトクリットが14%になり、緊急輸血を実施。この時点で血液塗抹標本を見てみると、初診時には全く検出されていなかった赤血球の寄生虫バベシア・ギブソニが多数寄生していることが判明。ガナゼック(大動物の駆虫薬)が届くまでドキシサイクリンを内服させたところ、溶血が改善し貧血の進行が止まったがヘマトクリットが上昇するまでには至らなかった。しかしガナゼックを1日おきに3回投与した時点でほとんどのバベシア虫体がいなくなった。ただよく見るとぽつりぽつりと寄生している赤血球が確認されたため4回目の投与を最後にしてみた所、赤血球には全く見らず、みるみるうちに貧血が改善していった。